「法令集の線引きって、どうやればいいの?」
「全部引くって、なんだか大変そう…」
「本当に意味あるのかな?」
一級建築士学科試験を受ける方、そんなふうに思ったことはありませんか?
僕も最初は同じように悩むところでしたが、直感でこう思いました。
「勉強はじめる前に法令集の線引きで何十時間も作業やってられるかぃっ!」
どうも。バウムくんです。
僕は平成30年度、一級建築士の学科試験に独学で一発合格しました。
中でも法規は30/30の満点!
使ったのは市販の法令集と過去問だけです。
(以下の記事で紹介しています)
そんな僕が伝えたいのは、法規の勉強も
「過去問をしっかりやった人が勝つ」
ということです。
この記事では、一般的な線引きのやり方と、僕が実際にやっていた
「問題を解きながら線引きする方法」について紹介します。
冒頭に記載した
「勉強はじめる前に法令集の線引きで何十時間も作業やってられるかぃっ!」
という想いを叶えつつ、
「過去問をしっかりやった人が勝つ」
という状態にするために、
「問題を解きながら線引きする方法」
によって試験に向けて仕上げていくという手法により、
高得点を目指そうとするものです。
ちなみに僕自身の実績として、一級建築士の前に受けた二級建築士、
後に受けた建築基準適合判定資格者のときもほぼ満点で合格できました。
-
二級建築士 → 法規満点!(その後の製図試験で落ちました)
-
建築基準適合判定資格者 → 考査A(択一問題です)1問ミスのみ
一般的な線引きのやり方
一般的には、例えばこんなふうに線引きします。するらしいです。
-
肯定の文章 → 赤線(「〜しなければならない」など)
-
否定の文章 → 青線(「〜してはならない」など)
-
他の条文を紹介している場所 → 黄色マーカー
-
数字や面積などの条件 → ピンクやオレンジ
さらに、
-
「または」「かつ」などの言葉に○や△の印をつける
-
条の番号に囲みをつけて目立たせる
などの工夫をします。
資格学校に通っている人は、学校から配られた「線引きの見本」をもとに、
法令集の最初から最後まで、全部に線を引いていきます。
例えば、TACさんは線引きの見本をHPで公開しています。
https://bookstore.tac-school.co.jp/statics/kenchiku2025/pdf/1q2025_vol1.pdf
なかなかカラフルな仕上がりで、これを手書きでやるのはかなり大変そうですよね。
(上のリンクは建築基準法だけしか含まれていないので、実際はもっとボリュームがあります)
しかも勉強を始める前にです。
線引きから試験対策が始まるそうです。
これは大事な部分をもれなく拾える反面、とても時間がかかります。
本当に全部やる必要がある?
僕は、見本どおりに全部線を引くのは効率が悪いと思いました。
というか、やってられない。やってられるかっ!
法令集って見たことありますか?
1000ページ以上あります。
ジャンプより分厚かったりします。orz
そこに全部線を引くのは、20時間以上かかるとも言われています。
気合を入れてぶっとおしで寝ずにがんばってもほぼ丸1日かかってしまうのです。
でも、実際の試験で使うのはその中の一部だけ。
4択×30問=120の選択肢の○✕を判断できればよいのです。
(4択のうちの1つが確実に○✕を判断できれば、ほかの3択は飛ばせます)
だったら、必要なところだけに線を引いた方がよくない?
その必要なところってどこ?ていう話になるかと思いますが、
正直言ってそれはわかりません。笑
当然といえば当然で、実際の試験で何が出るかはわからないので、
過去問や参考書の例題を頼りにするしかありません。
そう考えて、僕は問題を解きながら線引きするやり方にしました。
(これを勝手にバウム流と呼ぶことにします)
バウム流のやり方:問題を解きながら線引きする
僕は過去問もしくは参考書の例題をたくさん解いて、その中で出てきた条文を法令集で探し、その場で線引きするようにしていました。
やり方はこんなかんじ。
-
過去問を解く
-
該当する条文を法令集で探す
-
問題を解くために読む必要があるところに線引きする
-
他の条文を参照しているところも線引きする
この方法でとにかくいろいろな問題を解いていきました。
するとなんということでしょう!
-
線引きしながら読むから、内容をしっかり理解できる(けっこうその場で覚えられる)
-
問題の○✕を判断するために読むべきところに線が引かれるので、次に同じ条文を読むときにはスラスラ読むことができる
-
本番と同じ流れで法令集を使う練習になる
線引きをただの作業としてではなく、勉強の一環として取り入れることで、効率的に進めることができると思います。
たくさん解くことで、過去問で出た内容であれば、
線引きがされていた状態になっていて、試験の時に初見の条文を減らすことができます。
実際に過去問をさかのぼって解いていくと、
同じ条文を引く機会にかなり出くわします。
もし初見の条文にぶち当たったら、
そこは時間をかけて解けばよいって割り切るのです。
過去問で出た条文については、線引き効果を活かして、
時間をかけずに解くことができる状態になっていればOKです。
法規は法令集に答えがあるので、時間さえあれば解ける、
結局は時間との戦いです。
単に線を引く作業を行うよりも、
内容を理解しながらマーキングしていく。
っていうほうがよさそうと思えてきませんか?
またの機会に実際に僕が行った線引き事例などを紹介したいと思います。
(7/29 記事書きました)

この記事が、あなたの合格に役立ちますように。
バウムくんは、一級建築士を受験する方を応援しています。
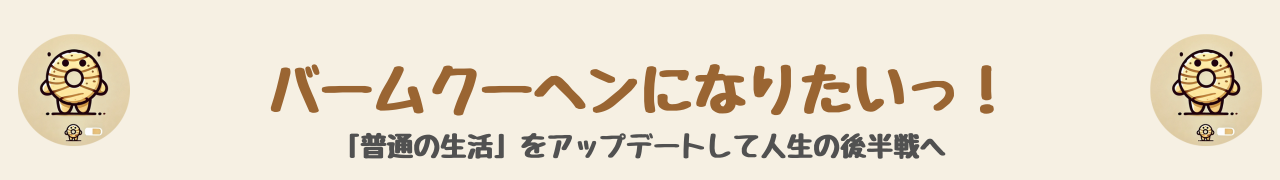



コメント